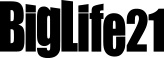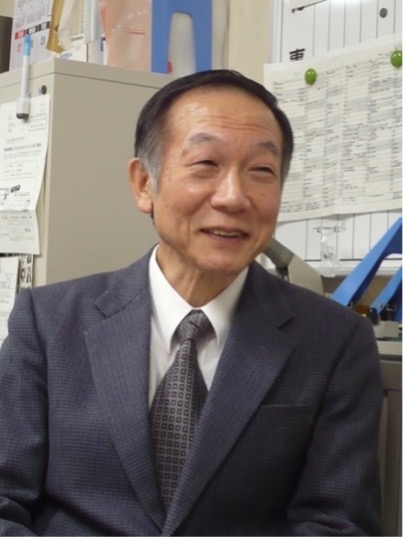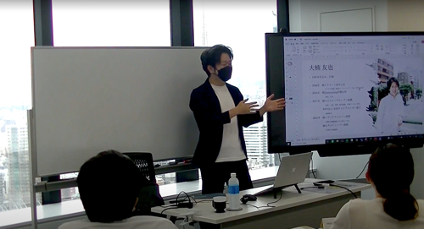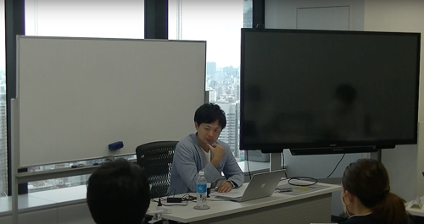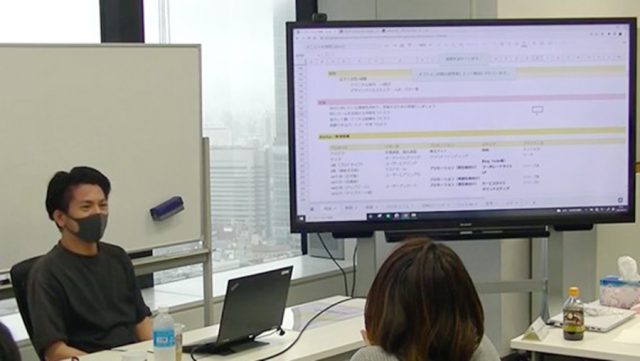日本発の稲作芸術 「田んぼアート」を世界に広めよ!
未来の沃野を拓け!ビジネスニューフロンティア 13
日本発の稲作芸術 「田んぼアート」を世界に広めよ!
©長谷川町子美術館 ・ 2012年に第二会場がオープン。従来の第一会場が縦長の絵柄に対し、第二会場は横長の絵柄が表現できるようになった。
約20年前、東北の村で始まった子ども向けの田植え体験が、いつしか「田んぼアート」という田んぼをキャンバスにしたアートの1ジャンルとなった。人口8000人あまりの村に年間約30万人が訪れ、観覧料だけで5000万円以上落とす。海外からの注目も高く、技術研修にも訪れる。田んぼアートのポテンシャルを追った。
それは、小学生向けの田植え体験から始まった
時は日本が昭和から平成に変わった頃。全国各地の市町村ではふるさと創成、いわゆる「まちおこし」が大きなテーマとなっていた。リゾート法やふるさと創成事業など関連法や政策も整備された。しかし青森県の田舎館村にとって、まちおこしのネタを見つけるのは至難の技だった。
田舎館村副村長の葛西幸男さんが当時を振り返る。
「米作り以外、これといった特長のない村でしたから。まず特産品を探そうと品評会を催していたのですが、4、5年目から参加が減ってきた。どうしたものかと考えていた時に、役場職員が『田んぼで近隣の小学生に田植えと稲刈りを手で体験させたらどうか』という提案が出た。
意義はあるとは思いましたが、我々米作り農家からすると田植えや稲刈りは仕事ですから、そんなことに参加する人がいるのかと思ってましたね。それで植えるだけではつまらないから、黄色、紫、地元のつがるおとめの3種の稲を使って文字と(地元の)岩木山を描いたのがはじまりです。
初年度の1993年は、弘前や青森から若いお母さんたちが子連れで130人くらい来ましたかね」
その時点ではまだ「田んぼアート」と言う呼び名はなかった。絵柄も四角い田んぼに三角の山を描いた単純なもの。毎年絵柄も変えずに続けた。
転機が訪れたのは2002年。10年目の節目ということで、当時の村長が「NHKの番組、『熱血!ふるさと対抗千人の力コンテスト』に応募してはどうか」と提案。場所も1000人が田植えできるよう役場庁舎前の広い田んぼを新たに確保した。絵柄も村内で公募し、より複雑な絵柄が採用された。
「面白いと思いましたが、そんなに集まるのか」と葛西さんは直前まで不安だったという。だがテレビの効果は大きかった。県内だけでなく県外からも参加者が集まり、番組の「インパクト賞」も受賞した。以後、1000人規模のイベントが定着、翌年は、「誰もがわかる絵柄」ということでモナリザが採用された。
「田んぼアート」の呼び名はこの頃から使われるようになったという。全国区のイベントとなったことで様々な意見も届くようになった。「この時多かったのはモナリザが太って見えたということです」(葛西さん)
ビューポイントである役場の展望台からだと手前が膨張して見えたのだ。こうした声を受け、翌年から絵柄は展望台からの遠近法で描かれるようになった。
CGに測量技術の先端を駆使。最後は職人の技
実は田舎館村の田んぼアートは、緻密でシステマティックな組織運営がなされている。
絵柄はまず田舎館村の「むらおこし推進協議会」のメンバーが協議の上、決める。この絵柄を村の依頼を受けた村内の中学校に勤務する美術教師がコンピューターで描いている。稲の配色や成長速度などを考慮し、絵柄の輪郭と配色を決め、最後に遠近法のソフトで変形をかけて調整するのだ。
当初3種類だった稲は徐々に増え、より複雑で立体感のある絵柄が生み出せるようになった。現在使用される稲は7色10種にまで増えた。その細やかな表現力に、「『いつ稲に色を塗るんですか』という問い合わせがいまだにあるんです」と企画観光課の福地香織さんは笑う。
画期的だったのは2008年に観賞用に開発された「ゆきあそび」という白い稲だ。とくに2011年の竹取物語では、光る竹の様子を表現して話題を呼んだ。
こうして精密に描かれた絵柄をもとに、田植えの設計図をつくる。どの苗をどの位置に植えるか、田んぼに線を引くための設計図だが、これも委託された測量士が専用ソフトを使って、ポイント位置を稲の高さを計算しながら割り出していく。
実際のポイントは測量機器を使いながら測量し、田んぼのなかに正確に打っていく。滑らかな曲線が描けるようになったのもこの測量技術の進化によるところが大きいという。
このポイント打ち作業は役場職員やボランティアの熟練農家などが1週間がかりで行っている。福地さんによれば、「この時期は役場の職員が半分くらい出ているので、役場内はがらんとしています」とのこと。ほかの業務が心配になってくるが、それだけ村にとっては重要な取り組みなのだ。
田植えは全国から募った参加者を含めた1200人規模で行うが、絵柄の細かい部分は役場職員や専門の農家が行う。それでも間違いが起こるという。稲が成長して間違いが発見された時は稲を植え直す。その管理も役場や農家の仕事となっている。
こうしたシステマティックな運営方法や技術開発は、国内外の範となっており、関係者が請われて技術指導に赴くこともある。近年は海外の関心も高く、田んぼアートそのものが海外にも広まりつつある。
「フランスや中国からも研修にいらしています。残念ながらフランスは稲が育たず田んぼアートはできませんでしたが、中国では観光地になっています」(福地さん)
第二会場増設で入館料設定。収入は5000万円に
田んぼアートへの期待は年を追うごとに上がっている。
だがレベルが上がれば関係者の負荷も大きくなる。田んぼアートの負担は基本的に村の予算や村民のボランティアに頼ってきており、長らく「人は来るが、経済効果に結びつかない」のが悩みだった。それまで募金形式での収入があったものの、決して手間暇に見合うものではなかった。
だが2012年以降、村は経済効果を高める積極策を打ち出す。従来の会場に加え、新たに村内の「道の駅」に専用展望台付きの第二会場を設置。この第二会場オープンを機に200円(小学生100円)の観覧料をとるようにした。さらに第二会場のアクセスを良くするために、村内を通る弘南鉄道に村が予算をつけ「田んぼアート」駅を設けた。また開催期間中はこの駅から第一会場を結ぶ無料のシャトルワゴンも走らせるようにした。
こうした取り組みもあって従来13〜15万人だった来場者もほぼ倍の29万人超まで増えている。1人がほぼ確実に2カ所を回っている計算だ。
観覧料を設定したことで2014年度は5240万円もの収入が得られた。来場者数からすると決して多い額ではないが、技術開発など投資に回る分が確保できたことは、事業継続の点からしても大きい。このほか期間中は第一会場前の駐車場スペースを地元の物産店舗に開放、第二会場となる道の駅の相乗効果を加えれば、経済効果はじわじわ上がりつつある。
田んぼアートは時期によってその表情が変化することが魅力だ。つまりリピーターが付きやすい。おみやげなど副産物を買えるしっかりとした戦略が立てば、経済の波及効果は広がるだろう。ちなみに見頃は秋のイメージがあるが、稲の色が出る7月から8月の夏。
田んぼアートの期待がかかるのは、2012年から開催されている「全国田んぼアートサミット」だ。すでに田んぼアートに取り組む団体や個人は日本国内で100以上にのぼる。サミットでは毎年持ち回りで、技術や人財育成の情報交換がなされている。
「埼玉県行田市さんが巨大田んぼアートでギネスに挑戦し、北海道ではバルーンを使った鑑賞法に取り組まれています。電車や山の上から眺める田んぼアートなど地域特性を活かした取り組みも報告されています。田舎館村としては今後さらに精度を上げて、点描などに挑戦していきたい」(福地さん)
紅葉前線を追うように、田んぼアートめぐりが定着する日も近いだろう。田んぼアートは、1つのアートジャンルを超え、新しい産業として進化を続けている。そのポテンシャルはまだまだある。
◆2015年6月号の記事より◆
WEBでは公開されていない記事や情報満載の雑誌版は毎号500円!
▸雑誌版の購入はこちらから