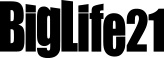世界平和研究所 小島弘氏・特別インタビュー【第1回】『そこにある歴史 敗戦~学生運動』
世界平和研究所 小島弘氏・特別インタビュー【第1回】『そこにある歴史 敗戦~学生運動』
◆インタビュアー:筒井潔 /文:加藤俊
1956年10月12日から13日にかけて─東京都立川市砂川町で、地元農民と武装警官隊が衝突。1195人が負傷、13人が検挙されるという大事件が起きた。後に「流血の砂川」と呼ばれ、「戦後学生運動の輝かしき成功例」とも称される砂川闘争(砂川基地拡張反対闘争)の一幕である。
この渦中に身を投じていた一人の男がいる。全学連で副委員長や共闘部長を歴任した、小島弘氏である。60年後の現在、小島氏の肩書は「公益財団法人世界平和研究所 参与」。この世界平和研究所とは、中曽根康弘元首相が会長を務める政策研究提言機関である。
かつて政府と戦った男が、現在では元首相の懐刀として仕えている。そこには、日本という国家の懐の深さを感じさせる面白い物語があった。本稿は、連載を通して小島氏の激動の人生を辿る。

小島弘氏 (公益財団法人 世界平和研究所参与)
■敗戦
筒井:今回は初回ということで、小島さんの学生時代のお話、学生運動に入っていく過程をお聞きしたいです。そもそもあの当時学生運動が異様な盛り上がりを見せたのは何故なのか。その時代背景をお聞きしたいので、終戦ぐらいまで話を遡った方が良いですかね。終戦時は、何歳だったのですか?
小島:小学6年生です。12歳くらい。
筒井:疎開していたのですか?
小島:そうそう。集団疎開でした。東京大空襲など、本格的に爆撃される前のことですよ。新潟の長岡でね。僕らのときは男だけ80人ぐらいお寺の寄宿舎みたいなのに行っていました。女性はまた別なところに行っていた。疎開にも色々あって、自分の親族が地方にいる人はそこに疎開させられました。縁故疎開ですね。
僕は集団疎開だから、学校で纏まって80名くらいと一緒でした。各県指定されるのです。葛飾区の人は新潟に。豊島区に住んでいたら長野県へ、とね。だから長岡に行った時は、当時戦死していましたけど山本五十六の家にも行きました。僕が小学校4年生ぐらいの時に山本五十六は戦死しているんです。国葬にも行ったのを憶えています。
筒井:国葬だったんですか。
小島:ええ。そういう経緯があるから疎開した際に、山本五十六の生家に行きました。
筒井:私は去年行ったんですけど、結構小さい家ですよね。コンパクトなお家で、2階建ての。
よく小説とか読むと、昭和20年の8月で世の中がガラリと変わったとありますが、長岡にいた小学校6年生の小島少年にとっては、終戦を意識する機会はどのタイミングだったのでしょうか。
小島:そう、子供でしたから、玉音放送は正直良くわからなかったです。後でね、「どうも戦争終わったらしいぞ」って大人が言っていて。実際聞いてはいたんですけど、何が起こっているのかは分からなかった。
筒井:そうすると玉音放送を聞いて、なんか起こったなっていうそれくらいの感覚で……。
小島:ええ。しばらくしてから大人の連中が「戦争終わったみたいだぞ」と口々に言い始めて。それからアメリカ兵がくるようになって。でもアメリカ軍なんてそれまで見たこともない。それこそ、アメリカ人がどうやって笑うのかも知らない。英語で笑うのか、どうやって笑うのか。小学校6年生だからね、分からない。
筒井:やはり軍国少年だったのですか?
小島:うん、だって僕ら小学校4年生のとき霞ヶ浦の航空隊に1日入隊しました。霞ヶ浦海軍航空隊では、朝礼に遅れてくる者もいたんですよ。
筒井:ええ! その時点で、モラル下がっているじゃないですか。
小島:そう。聞いているのと、実際の兵隊の世界は、随分違うなとは思いました(笑い)。
筒井:でも小島さんの世代ですと、小学校あたりで憧れの職業っていうと……。
小島:そう、やっぱり軍人が多かったですね。
筒井:そうですよね。学校を出たら、軍人さんになってというエリートコースが確立されていたんですものね。
小島:まぁ、エリートなんて言う言葉は当時ないけどね。国の為に皆頑張ろうって意識はあった。
■大人は信用出来ない
筒井:でも、そうした意識も敗戦を境にガラリと変わったんですよね。戦前に大人が言っている言葉も180度変わったとはよく聞きますけど。そういう変節を間近で見て、大人に対する見方は変わりましたか。信用できない、とか。
小島:そりゃ、そうですよ。信用できなかったね。特に、教員なんかは。昨日まで「撃ちてし止まむ」って言っていたのに、戦後になったら民主主義だって。本当にコロリと言うことが変わったんです。それに対して、「なにが民主主義だよ!」という思いにならないわけがない。
筒井:その大人に対する不信感って、資本論とかそういうところに走らせる遠因になっているのですか。
小島:それは多分にあると思います。要するに、戦争にしろ、教育にしろ、全部大人側がやったことと思っていた。それを「間違えました、戦争終わりました、今日からは新しくこの考えで行きます」って言われて、すんなりと納得はできなかった。
筒井:子供に対して謝った人とかいたんですか?
小島:いない、いない(笑い)。
筒井:ちょっと立ち入ったお話ですけど、親に対する感情はどうお持ちだったんですか。
小島:それは全然ないです。うちの親父もね、身体が悪くて、実際兵隊には行かなかったけれど、終戦が8月15日でしょ、8月20日入隊で召集令状が直前に来ていたんですよ。うちの親父は、「俺が戦争にいくようじゃ日本も終わりだな」なんて言っていました。そのとき31歳でしたけど、20歳の時には合格しなかったんです。体が弱くて。
筒井:敗戦して、食べて行くための思考の切り替えはすんなりとできたのですか?
小島:そこはね、できません。でも、戦争中から食うや食わずだから。8月15日以前と以降で、生活が極端に変わるワケではなかった。ただ、日本軍の生活物資は随分出回りました。それで裕福に暮らせるってことはないけど。後は、駅前に闇市ができましたね。
筒井:お父様なんかは家族をなんとかして食べさせなきゃいけない、それは大変な思いをなさったのではないですか。
小島:そう、それが一番ですよ。
■満州帰国組はハイカラだった
筒井:そういう激変する環境で多感な時期を過ごすことで、社会に対してはどういう思いを持ったのですか?
小島:終戦のときはまだ中学に入る前ですかね。それから数年の間はやっぱり戦争に対するね、なんでこんなバカな戦争をやったんだという話が、色々出てきたんです。その上、兵隊さん達が、だんだん引き上げて日本に戻ってきました。これも、勝って引き上げてくるならいいですけど、負けて引き上げてくるワケです。傷痍軍人の方が大勢いました。兵隊だけじゃありません。僕らと同世代の連中にも、満州帰りは多かった。
でもですね、実際、日本にいた連中よりも、満州に行った人の方が良い生活をしていましたから。あっちでは植民地の統治下だから良い生活をできていたんです。
筒井:そうした満州から帰って来た子供はいじめにはあわなかったんですか。
小島:あわないです。当時外国にいたって言ったら彼らしかいないんだから。だから僕らが知っているハイカラな奴等はみんな満州がらみだった。で、そういった連中は、頭がいいから、帰って来て国立に入る人が多かった。(※)香山健一君や篠原浩一郎君なんかがそうだよね。
だから、植民地で収奪したとか言われているけれども、一方で、後藤新平を始め、あの頃の若い官僚には、立派な行政官の方も多かった。一概に悪い面ばかりではなかったと思う。実際、戦後の復興にしても、そういった植民地統治に関わった若い人材がいたからこそ成し得たというところはあります。彼等が多く関わっていますから。当時一兵卒で植民地にいた人達は、現地で、真っさらな所にダムを作ったり、一から社会を築き上げていったワケです。そういった人達が戦後日本に帰って来て、官僚になり日本の復興を担ったのです。
筒井:そうですよね。よく言われているのが、そういった若手世代の上の世代40代、50代の人間がパージされたことも大きかったと。戦犯追放になって。そのため、30代で偉いポストに着く人が多かった。『三等重役』なんて小説も昔ありましたね。
■学生運動が起きた背景
筒井:私、今日の主題の一つに、なぜ学生運動だったのかっていうのが、問題意識としてあるのです。
小島:僕達の世代では、高校の時は共産党で、大学では学生運動をというのが多かったんです。当時の雰囲気がね、当時労働組合が力を持っていて、労働運動が激しかった。もう一つの背景として、さっきお話ししたように、敗戦を境に言うことがまるっきり変わった上の世代への反発という意識もあった。
僕の場合は、高校の頃、近くに日立の工場があったのですが、そこの工員さんの影響が大きかった。共産党に熱心な方が多かったんです。彼らが僕ら高校生と付き合ってくれて、それで感化されましたね。
筒井:今の日本では考えられないことですよね。近所のおじさんと高校生が一緒に活動するって。
小島:おじさんと言っても、労働組合の青年部の人だから、歳はそんなに変わらなかった。で、最初は僕らもよく分からなかったんですが、勉強という形で色々と教わっているうちに、のめり込むようになったんです。一生懸命「共産党宣言」とか読みましたもの。
筒井:そういった方達との付き合いというのは、いつまで続いたのですか。
小島:大学に入ったら、今度は大学の連中と付き合いました。あの当時大学には同じような連中がゴロゴロいたんです。
筒井:そうすると、大学でも勉強会をやられて。高校のときにこんな勉強会をやっていたってそういう人たちが集まって。
小島:要するに、共産党の連中はオルグに来るから、学生運動していると。今はそういうこと全然ないと思いますけどね。
筒井:オルグって殆ど死語になっているので、あえて質問しますが、英語だとオーガニゼーションじゃないですか。小島さんが大学に入ったときにオルグというのはもう存在していたんですね。それはどれくらいの人間の規模だったんですか。
小島:東大の細胞は、300人ぐらいいたね。大きな教室で共産党の会合がありました。今は300人学生が集まるなんて難しいでしょ。コンサートとかない限り集まらないでしょ。当時は社会全体がね、そういう雰囲気がありましたから。50年から6年くらいじゃないですか。
筒井:55年から56年。まさしく、戦争が終わって10年ぐらい。1956年の「経済白書」では、もはや戦後ではないとかって言い出した頃ですね。
小島:そう、社会全体がそういった雰囲気だった。戦後ではないと言い始めてね。僕らの歳は戦争に行ってないけど戦争を体験していますので。疎開させられた経験もありますしね。まあ、ひとことで言えるのは、僕が学生運動をやっている時と言うのは、砂川闘争や安保闘争があったときです。要は、学生運動が一番盛り上がったときなんです。砂川闘争では、実際に、アメリカ軍の基地拡張を阻止できたんですから。今の世の中じゃあ、沖縄だって阻止できないでしょ。
筒井:現代では無理ですよね。というより、基地を阻止できたのは、砂川闘争だけですよね。これって戦後の学生運動の唯一のビクトリーというか、サクセスストーリーになるのですよね。
小島:そう、それで安保闘争で締めくくりだから、こりゃあいい時期でした。
筒井:いい時期なのか、それとも小島さんとか森田実さんとか、ああいう各方々がいたからいい時期になったのかっていう、因果関係はどっちなのかっていう。
小島:それはどうだろう。でもこういうことはありますよね。砂川闘争の時は──(次号に続く)
※砂川闘争(砂川基地拡張反対闘争)とは、米軍が、基地を拡張するために、在日米軍立川飛行場に隣接する砂川町の約5万2000坪を接収しようとしたことに、学生や町が反対闘争を行った住民運動である。第1次砂川闘争は1955年でそれほど注目されなかったが、1956年10月の「第2次砂川闘争」では、当時東京大学の学生だった森田実※(現在、政治評論家)等の指導する学生運動によって測量が中止となった。そのため、地元で「勝った、勝った」と大騒ぎになり、学生運動が盛り上がるきっかけとなった。最終的に、米軍は1968年12月に滑走路延長を取りやめ、翌1969年10月には横田飛行場(横田基地、東京都福生市)への移転を発表している。
森田実:1932年生。東京大学卒。日本の政治評論家。株式会社森田総合研究所代表取締役。在学中に日本共産党に入党し、香山健一、島成郎、生田浩二、青木昌彦らとともに全日本学生自治会総連合の指導部を形成した。破壊活動防止法反対闘争(1952年)、原水爆禁止運動(1955年)、砂川闘争(1957年)、安保闘争(1958年〜1960年)などに携わる。後年、テレビのコメンテーターとして活躍する。
香山健一:1933年生。東京大学卒。日本の政治学者。元学習院大学法学部教授。元全日本学生自治会総連合(全学連)委員長。
篠原浩一郎:1938年生。九州大学卒。全学連中央執行委員。60年安保当時は社共同(社会主義学生同盟)委員長。卒業後、機械メーカー等を経て、現在はNPO法人のBHNテレコム支援協議会常務理事。安保闘争時13回逮捕。闘争後、一時山口組系列に。親分に「何なら全学連と山口組と一回戦ってみましょうか」と冗談を言ったという逸話がある。
◉プロフィール/小島 弘氏
1932年生。明治大学卒。57年全学連第10回大会より全学連副委員長。60年安保闘争当時は、全学連中央執行委員及び書記局共闘部長。その後、新自由クラブ事務局長を経て、現在は世界平和研究所参与。
◉インタビュアー/筒井 潔
経営&公共政策コンサルタント
慶應義塾大学理工学部電気工学科博士課程修了。
外資系テスターメーカー、ベンチャー企業サラリーマンと並行して、財団法人電子文化研究所(創設者松下幸之助)技術顧問をはじめ、財団法人評議員、一般社団法人監事、一般社団法人理事などの公益団体の立ち上げや運営に携わる。大学の研究成果の事業化のアドバイザとしてリサーチアドミニストレータも経験。現在、合同会社創光技術事務所代表社員兼所長、株式会社海野世界戦略研究所代表取締役会長、株式会社ダイテック取締役副社長などを務める。
共訳書に「電子液体:強相関電子系の物理とその応用」(シュプリンガー東京)、共著所に「消滅してたまるか! 品格ある革新的持続へ」 (文藝春秋企画出版)がある。