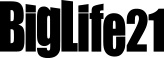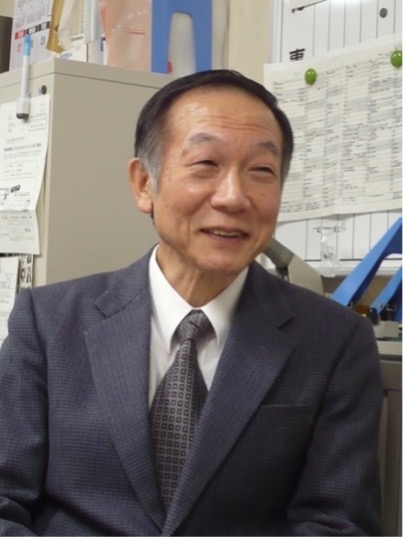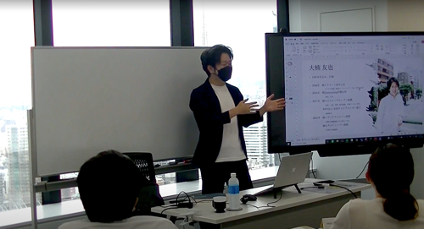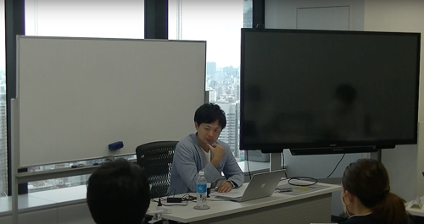脱石油時代がやってくる 昆虫テクノロジーが未来を変える! 東京農業大学長島孝行教授
未来の沃野を拓け!ビジネスニューフロンティア
脱石油時代がやってくる 昆虫テクノロジーが未来を変える!
◆取材・文:佐藤 さとる
かつてはお家芸だった家電やパソコンも気がつけば韓国や中国企業にその座を奪われた。自動車も生産拠点そのものはどんどん海外に移っており、産業じたいの行方は厳しい。日々変化の激しいIT産業も依然アメリカがリードし、新興国に煽られている。期待のロボットも一般市場を獲得するまでには至っていない。
しかし日本のポテンシャルはまだまだ高い。まだ知られていない、開拓されていない産業がある。その1つが昆虫産業である。その最前線の先には広大な沃野が広がっていた…。
着色塗料フリーでステンレスに色が着く

これからは、色は「塗る」ものではなく、「加工する」ものに変わるかもしれない―。
新潟県燕市にある株式会社中野科学では、メッキや着色塗料を使わないカラフルなステンレス容器を製造している。カラフルな色は表面の透明皮膜の厚みを1万分の1ミリでコントロールすることで生み出される「干渉色」。ステンレス自体に色はなく、光の屈折率の差によって色が違って見える。
このカラーステンレスは、従来の製造工程で用いられる透明な酸化皮膜を加工するだけなので耐薬品性などは従来のまま。キズがついてもそこから塗料やメッキが剥がれることはない。無垢のままのステンレスであるため、そのままリサイクルも可能だ。
この技術を提供したのが、東京農業大学の長島孝行教授。昆虫が持つ機能や生産物を研究応用するインセクトテクノロジーで、モノづくりの新しい地平を切り拓いてきた。この塗料フリーのカラフルステンレスは、玉虫の研究から生み出された。
玉虫のきれいな「玉虫色」は、体表面に色がついているのではなく、翅の表面構造が光のスペクトルをコントロールすることで生み出されている。長島教授はこのメカニズムを応用し、すでに200種以上もの色が出せるようになった。
「表面構造による発色は、化学塗料で着色していないので、構造が壊れない限り、色褪せない。そのまま無垢材としてリサイクルもでき、コストも減らせる。当然環境に与える負荷も少なくなり、アレルギーの心配もない。携帯電話やPCなどの電子機器や家電、乗用車などさまざまな用途で応用可能」(長島教授・以下同) という。
こうした表面構造による干渉色は自然界には溢れている。コガネムシの表面や蝶の翅、あるいは孔雀の羽なども同様のメカニズムを持つ。
蚕の繭に秘められた驚異の機能
長島教授が最も力を入れているのは、カイコが生み出すシルクの応用だ。明治時代、日本の近代化を牽引してきた養蚕技術は、欧米の追随を許さないほど高い。その研究の対象は、
「カイコにいかに多くの糸(シルク)を吐かせるか、いかに細く均一な糸をつくらせるかの2点だった。カイコそのものがどのような機能をもっているかなどには関心を持たないで来た。そのため、カイコがなぜ繭をつくるのかというメカニズムも十分に解明されてこなかった。体の余分となったアミノ酸を吐き出すのだと。つまり繭は蚕の体内から吐き出されたごみだと思われていた」
しかし長島教授がその「ごみ」に着目すると、驚くべき機能が次々と判明する。
たとえばシルクの紫外線(UV)カット機能。養蚕のシルクは発がん性の高いB波を90%以上遮断する。さらに野生種の蚕からできるワイルドシルクと呼ばれるものには、A波、C波の紫外線を90数%カットできるものもある。
長島教授はこの性質を大きく応用し、UVカット機能を盛り込んだ衣類や日傘を開発、販売までしている。さらに研究を進めると、シルクに制菌性や、脂肪を吸収する機能があることも分かった。
長島教授はシルクの液体化、粉末化にも成功し、これをもとに化粧品や健康食品、医療素材を開発。ベンチャー企業を興して販売まで手がけている。いずれもリピーターがつく人気ぶりだ。
またシルク産業の発展のために養蚕業を復活させるべく、農家を訪ねてはカイコの餌である桑の栽培協力を依頼している。桑の研究を重ねて、血糖値を抑える効能を発見すると、桑のお茶や桑の粉末入り菓子・食品を共同開発し、その用途を拡げている。さらには行政や学校と連携し、シルクと教育、観光などを絡めた地域産業の振興にも力を注ぐ。
海外にも足を伸ばす。海外の野山を歩き、金色や銀色の糸を吐き出す蛾を見つけ出し、現地の行政や人々と協力しその産業化を図るなど、科学者の枠を超えて活動している。
研究者も企業人も「一人学際」でフットワークを広げる
実は日本は昆虫研究大国である。植生が豊かな日本は、外国に比べても昆虫種が多い。昆虫との共存関係は縄文時代からと古く、昆虫研究は進んでいる。ただそのほとんどが昆虫の生態研究に留まり、メカニズムや生産物をモノづくりや生活に応用するという思想は乏しかった。
近年、蚊の口のメカニズムを応用した、刺しても痛くない注射針や、人工蜘蛛糸の大量生産化などの事例が出ているが、まだまだそのポテンシャルが活かされているとは言いがたい。研究環境もさることながら、モノづくりにつなぐ連携が不足しているからだ。
長島教授の許には日々さまざまな企業関係者が訪れているが、長島教授自らも中小企業に出向き、その試作化、製品化のための交渉を行う。
「結構行き当たりばったりで出かけてます。効率が悪いと思うかもしれませんが、すれ違いやムダがあったほうが面白い発想に出会える。よく産学連携と言いますが、連携しただけでは何も生まれない。間に産業と科学を結ぶプロがいないと。
アメリカの研究機関はそういうプロのマネージャーがいる。研究のことが全部わかって、あの企業、この事業と結ぶことができる。日本はいそうでいないんです。そういう人は評論家や解説者になってしまうから。
僕はもったいないと思う。もっと中に入って当事者としてやってほしいですね。それから学者はもっとそとに目を向けないと。枠を決めてそこのなかで留まっていないでフットワークを広げるべき。僕は『一人学際』って言ってますが(笑い)。それは企業側にも必要だと思います。そういう人たちが出会うともっと日本の社会は面白くなる」
いま日本の産業はさまざまな変革期に入っている。今後100年を考えた時、出てくる答えは「持続可能な社会」だ。再生不可能な資源はいずれ枯渇する。「そのためにはまず石油依存から脱却すること」と長島教授。
「日本の中小企業の方は本当に素晴らしい。僕が『こんなものできないか』って言って、できなかったことがまずないんですよ。ただ昆虫や自然を真似て人工的につくるのでは意味がない。そこに自然そのものを活かす、生き物を守る仕組みがないと。その技術も、社会が持続しませんから」
昆虫は世界中に100万種いるとされる。この膨大な眠れる沃野を活用しない手はない。行政、金融機関の踏み込んだ取り組みがいまこそ必要だ。

◆2014年4月号の記事より◆
▸雑誌版の購入はこちらから