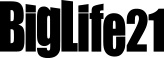塚田理研工業株式会社
「非常識」に挑戦し続けて半世紀

塚田理研工業株式会社 代表取締役 下島 康保氏
スタートは出逢いからだったが、常にアンテナを高く掲げて将来を予見して改良、革新を続けて業界のトップ企業に成長した。それは、新分野を開拓する「非常識」への挑戦の連続だった。社長の経営理念は、「今を最低と思え」「5年後の常識」。一丸となってそれぞれの持ち場で新しい問題点を掘り出して挑戦する社員たちをリストラしたことは創業以来の半世紀、一度もない。
3K5Kとは無縁のメッキ工場

メッキは3K、5Kの代表的な、いわば公害を産む代表のように考えられている業種である。が、塚田理研工業の工場は、金型から組み立てまでの全工程を一貫生産の複合全自動ラインで作業を行い、搬送ロボットが黙々と作業を進めるので人間が直接手を触れることはなく、きつい、危険、汚いとは縁遠い。また、床が木製なのは水に濡れないからで、立ち仕事でも疲れないための配慮である。
さらに、メッキ工場特有の臭いをほとんど感じないのは、汚れた空気を浄化して外に出し、外のきれいな空気を取り入れるシステムを導入しているからである。
この居心地のよい環境への配慮はいたる所に見られる。例えば、万一の事態に備えて本社工場で必要とする電力以上の2000kwの自家発電機を装備し、地下に150トン分の液体を貯蔵出来るタンクを設置して排水漏れに備え、3カ月に一度の訓練をしているのだ。
時代をリードする革新的で清潔なメッキ工場は一品生産から77種類の大量生産が出来る能力を備え、約300社の顧客を持ち、年商は約40億円である。
それは出逢いから始まった

しかし、順風満帆でこの状態になったのではない。「うちは元々材木屋だったのですよ」と下島社長が言うように、下島社長が志を立てて創業したのではなかった。
地元の高校を卒業した下島社長は材木商に将来性を感じなかったが、3年間で結論を出すという父親との約束で一旦家業を継いだが、3年後に東京に出て電子計測器の会社に就職した。当時はプリント基板がクローズアップされだした時代である。
塚田理研工業が設立されたのは1963年だが、その前身となったのが塚田理化学研究所で、旧陸軍の疎開工場技師だった塚田藤一氏が終戦直後から電気メッキ技術を開発していたのである。
その主なテーマが、新時代の素材として脚光を浴びていたプラスチックへのメッキで、技術的に難しいとされていたものだったが、試験管レベルでは成功していたが、こんなものに取り組むのは「非常識」とされていた。しかし、塚田理研工業は創業当時からその非常識に挑戦していたのである。
この研究に興味を持ち、塚田氏と意気投合した下島社長の父・伝一氏が出資し、塚田氏を社長として塚田理研工業を設立したのだった。
そして東京にいた下島社長も参加した。プラスチックへのメッキがプリント基板に役立つとの期待もあったのである。
ところが、会社創立から半年ぐらいして塚田氏は脳溢血で急逝した。伝一氏が社長となり、下島社長を開発の中心として事業は継続されたが、「社名は変えないでくれ」と言う塚田氏との約束は守られた。
ちなみに、会社の所在地は、今は開発されて面影はないが、当時は人里離れた不便な場所で、ここを選んだのは、排液で人々に迷惑をかけない配慮からだった。だから、今、最先端の環境保全システムを導入しているのは時流に乗ったものではなく、創業以来の哲学なのである。
1971年に水質汚濁防止法が出来ると、早々とイオン交換式総合排水処理装置を自社研究して設置した。排水をリサイクルするのである。しかし、保健所は排水を酸化還元して処理するのではないので「公害防止装置ではない」と言って認めようとしなかった。これも世間から見ると非常識だったのだ。
会社を創立し、新技術のプラスチックメッキは注目されたが、当時の地元では大きな需要も無く、東京や名古屋に営業に行っても、零細の地方の会社は大手企業から相手にされるはずもなく、面倒を見てくれたのはスタンダード工業などわずかなものだった。
低空飛行から全自動の量産態勢に
やっと低空飛行から脱出できる兆しが見え始めたのは1960年代の高度成長期になってからである。1966年にバレルによるプラスチックメッキの量産化に成功していたが、60年代後半になるとプラスチックが日用品にも多用されるようになり、プラスチックメッキの意匠性が高く評価されて婦人服のボタンの注文が増えたことで会社は成長し、量産化への道が開けたのである。
1973年はベトナム和平協定のほか、水俣病訴訟ではチッソ水俣工場の排液が原因だと認定され、パレスチナ解放人民戦線と日本赤軍の混成部隊が日航機をハイジャックして福田赳夫首相に「超法規的措置」をとらせるなど、歴史に残る事件が起きた年だが、塚田理研工業でも当時、工場長の下島社長が1億円を投入して全自動メッキラインを建設するという画期的な出来事があった。
コンピュータ制御によるものだが、コンピュータの珍しい時代にメッキ用整流器メーカーの技術者と組んで手作りしたものである。職人が永年の経験と勘で多品種少量生産するのが業界の常識だった時代である。しかし、十畳ほどもある巨大な装置は思うように作動せず、「工場長の大きなおもちゃ」と揶揄されたものだった。おまけに、試行錯誤の末にやっと完成した翌年にはオイルショックに見舞われたのだった。身分不相応な投資の末の痛手だったが、これによって生産効率が上がり、品質が向上することで他社との差別化を図ることが出来たのだった。

現在はさらに進歩して、冒頭で触れたように、「金型→射出成形→メッキ→塗装・印刷→組み立て」の一貫生産システムとなり、メッキ工程は120mの複合全自動ラインとなっている。全てバーコード入力によって多種多様な製品、仕様、生産ロットに的確に対応出来るのである。
常に新しい「非常識」に挑む下島社長だが、「時代の流れを掴むと、基礎から研究・開発するのではなく、すでにある技術を応用しているだけ」だと気負い無く話すのを見ると、角倉了以(すみのくらりょうい)のことが思い出される。
角倉家は金融、貿易などで富を築いた豪商だが、高瀬舟が有名なためか、角倉了以は一般に「水運の父」として知られている。
了以が先ず手を付けたのが京都の西を流れる大堰川(保津川)だった。丹波の材木の需要が増大していたが、岩石の多いこの河を輸送のために開削するのには技術的にも資金的にも「非常識」だとされていた。が、了以は旅先で見た喫水の浅い「高瀬舟」をヒントにしたのだった。高瀬とは浅瀬のことで、高瀬舟は奈良時代からあったものである。
開削の許可を得ると、僅か6カ月後に竣工させているが、特に新技術を開発したのではなく、従来の技術を有効に組み合せたものである。この成功によって運上金(通行税)を取る権利を独占し、投下資本の何倍もの収益を得たが、丹波地方の材木だけでなく、鉄や石材、農作物が大量に運ばれて農民は潤い、嵯峨近辺は商人の往来が多くなって発展し、京・大坂の物価は下がったのである。
家康は富士川の開削に続いて天竜川の開削を命じた。また、高瀬川の開削では、田の買収に当って、了以は買収や工事に伴う損失は全て弁償し、諸々の保証をした誠実さは、常に水が濁らないように汚水抜きの装備を配置する環境に配慮した技術面にも現れている。
元来、角倉家は商人であると共に代々医者の家系でもあり、理科系の血筋なのだ。が、それよりも、強権が通用する時代でのこの配慮は、技術や世俗的なことよりも、むしろ人間性によるものであり、下島社長親子が会社の建設用地として人家の無い場所を選んだことと通じるものがある。
最新技術と将来性
従来、耐食性や防食性が高く、量産に向くことからメッキの主流だった六価クロムは毒性が強いため、塚田理研工業では業界に先駆けて毒性の無い三価クロムへの転換を全自動ラインで実施し、六価クロムと同等の製品を製造している。

排水についても、2005年に総合排水リサイクルセンターを建設し、排水に含まれるニッケルや銅、クロムなどの金属資源を高純度で回収し、スラッジ(金属と液体の混合物)にして製錬所に販売している。今までは産業廃棄物処理業者に費用を払って処理してもらっていたのでその差額は大きく、このリサイクルプラントそのものの販売も行っている。
この装置による排水のリサイクル率は50%だが、今年中に80%にし、近い将来は100%を目指すという。また、2008年にはボイラーの燃料をCO2の排出量の少ない液化天然ガスに切り替えた。
下島社長の「非常識」は技術面だけでなく経営方針や人事面でも発揮される。冒頭で触れたようにリストラをしたことが無く、終身雇用であることや経営情報は全て公開して、やる気のある社員を登用するのはもちろん、課長以上の管理職に欠員が出ると、社員全員による投票を参考にして決めるというが、社長人事も例外ではないというのだ。投票ではないが、徳川家康は、意見の分かれそうな重大事項はよく家臣に意見を問うた。問う前に結論は出していたが、問われたことで家臣は納得した。これが徳川長期政権への手法であったのだ。
今は、プラスチックとは思えない質感を持った製品を産む技術を開発し、塚田理研工業の色見本が業界のスタンダードになっているが、会社とメッキ業界の見通しについては、「今の政治では将来はない」と強い口調で言った。それは、民主党政権のみならず自民党を含む全政治家に向けられたもので、政治と経済は切り離せず、「変化する社会に対応しなければ企業は倒産するが、政治家は社会の変化に鈍感過ぎる」と続くのだ。
戦後の復興時には政治は経済を助け、環境を作り、二人三脚で成果を上げたのである。その結果、癒着や利権が生まれたのも事実だが、今のように無自覚で経済の足を引っ張る方が罪は重いのだ。選挙に出るのはバッジを付けるのが目的で、政治家に志が無くなったのである。
このままでは、会社存続のためには海外にマーケットを求めざるを得ない。下島社長はインドの企業と合弁を決めた。5年後にはインドは中国並になると予想しているのだ。そして、中国との話も進行中だという。

下島 康保(しもじま やすほ)
1937年生まれ、長野県出身。1956年、地元の赤穂高等学校を卒業後、三年間の約束で家業の材木商を継ぐが、東京の電子計測計測器会社に就職。1963年、塚田理研工業を設立と同時に入社。1996年、代表取締役に就任。現在に至る。
塚田理研工業株式会社
〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂16397-5
TEL 0265-82-3256