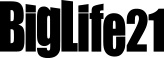株式会社タグチゴム – 堅調な海外展開を背景に、目指すは「ゴムの総合商社」

〈モノづくりの挑戦〉
株式会社タグチゴム – 堅調な海外展開を背景に、目指すは「ゴムの総合商社」
◆取材:綿抜幹夫
創業67年のゴム加工業、株式会社タグチゴム。早期に海外進出を果たし、マレーシアを中心に東南アジアで実績を残してきた。現在の同社は、創業者の孫の三兄弟が、社長である父を助け、それぞれ国内や海外拠点の経営にあたる。次男・田口郁男氏(常務取締役)と、折良く帰国中だった長男・田口徳明氏(専務取締役)から話を聞いた。
◎タグチゴム沿革
■早かった海外進出
1948年、両氏の祖父によって創業された「田口ゴム工業所」。1956年には「有限会社田口ゴム工業所」として設立、以来3度目の移転で現在の地に工場を構え、1976年に改称して「株式会社タグチゴム」となる。創業当初の顧客は玩具メーカーが主で、一世を風靡した「チョロQ」のタイヤのほとんどを手がけていたほか、ラジコンのタイヤにおいても大きなシェアを占めていたという。
1980年代に入ると、顧客のほとんどが海外に進出。同社も追いかける形で、1987年にシンガポールに工場を設立した。やがて玩具メーカーはシンガポールから撤退したが、入れ替わる形で続々と進出してきたのが弱電関連だ。日系の弱電関係企業との取引が拡大し、1990年には玩具に代わって白物家電などの工業用品が主力となった。現在でも、メインとなるのは弱電関係、続いて自動車関係、建材関係が大きな3本の柱となっている。加えて、医療系部品や、祖業である玩具もわずかながら製造している。
■海外と国内の差別化戦略
海外生産が全体の9割を占める同社。比較的早い時期にシンガポール進出を果たしたことが転機となり、今日の礎を築いた。二代目である現社長、田口勝也氏が就任後の1993年には工場をマレーシアに移転し、マレーシアを中心にタイやシンガポールなど東南アジアに広く展開している。「海外のタグチゴム」をPRするため、ウェブサイトも海外向けに英語版を公開している。
同社全体としては9割が工業用品というが、海外ではその割合は100%だ。大量生産を手がけ、ISOも取得している海外と区別し、国内では重要保安部品や特殊部品など、少量多品種生産に絞って製造。顧客の細やかなニーズに対応しながら、付加価値の高いモノづくりを行う。今期の売り上げはグループで約6億円。業績は横ばいだが、黒字は確保できているという。人件費削減やコストダウンに努め、生き残りを図る。
■今後の展望
「お客様の海外シフトが今後も続く限り、ゴム産業での国内回帰は難しい」と語る郁男氏。同社の製品は、受賞歴もあるなど海外では評価が高い。引き続き、東南アジアを生産拠点に高品質・低コストを武器に生産を続け、海外では国内で展開が難しくなった製品も伸ばせると見込んでいる。
一方で国内では、付加価値の高い特殊品の開発に注力。「メイド・イン・ジャパン」の品質を保ち、海外の顧客へのアピールも狙う。国内市場は今後も縮小すると同時に、競合の数も減っていく。残ったパイの中で、いかに利益を確保するかが鍵を握る。
常務取締役 田口郁男氏
◎国内戦略(常務・郁男氏)
■葛飾ゴム工業会
かつてのゴム業界は、創業オーナーの頃の時代背景もあったためか若干閉鎖的だった。今でこそそういった面は薄れてきてはいるが、約60社が所属する「葛飾ゴム工業会」の理事を務める郁男氏は、そんな旧来の風潮を変えようとしている。
郁男氏ら40歳代を中心とする経営者たちは、この先30〜40年は働ける。こうした長いスパンで考えたとき、自分たちが現在持っている技術のみでの事業継続に危機感を禁じ得ないという郁男氏。他社は、より良い方法で、コストが下がる方法を編み出しているかも知れない。一方で同社も、マレーシアで独自の技術やノウハウを学び身につけてきた。
そこで郁男氏は、業界内で若手を中心に情報公開・交換に否定的でない経営者を集め、互いの技術を持ち寄り、公開会をしないかという働きかけを行っている。独自の技術は、それぞれの会社の生命線とも言える競争力であり、隠そうとするのは当然だ。しかし、葛飾区という地域全体や業界全体という大きな視点で見たとき、日に日に同業者が倒れていく状況にあって、互いに切磋琢磨し、ともに高いレベルへ上っていくことこそが重要だろう。そのためには、積極的な情報交換や技術の公開が有効だ。
■『ものコト100』
業界内への呼びかけと同時に、同社は2015年7月に立ち上がった葛飾区の若手経営者を中心とする異業種交流会「ものコト100(ワンハンドレッド)」に加わり、郁男氏が会長を務めている。ゴム製造業の同社のほか、金属加工業、建築関係、デザイナーなどさまざまな業種業態の経営者が集まる同会では、会員同士の情報交換やコラボはもちろんのこと、異業種メーカーの工場見学を企画するなど、盛んに交流を行っている。交流の中から新たなビジネスの芽を生み、需要を増やすことが狙いだ。
■目指すは「ゴムのワンストップショップ」
顧客のニーズは、大量生産から、オーダーメイドも含めた多品種少量生産へとシフトしている。郁男氏が目指すのは、「タグチゴムに頼めば、ゴムに関するすべてのモノが揃う『ゴムのワンストップショップ』」だ。そのために、協力メーカーとの協業体制をより強固にしている。場合によっては商社のような立場も取りながら、金型レスでの低コスト生産など、幅広いニーズに応えていく。
得意とする大量生産へのニーズにも引き続き対応しながら、これまでとは違ったサービスを展開することによって、ゴムに限らないさまざまなニーズへの可能性を広く探る。同社、協力メーカー、顧客のすべてにメリットをもたらす柔軟な立場を取れるのは、フットワークの軽い中小企業なればこそだ。
専務取締役/シンガポール・マレーシア現地法人代表取締役 田口徳明氏
◎海外戦略(専務・徳明氏)
■地産地消の海外拠点
同社の海外法人では、現地で顧客を開拓し、9割以上を現地で販売している。戦略として、日本本社の仕事を行わないようにしているといい、日本からの仕事はわずか数%に過ぎない。海外で安く作ったモノを日本で販売するための、単なる子会社としての海外工場ではないのだ。そうした親会社に搾取される関係性では、資金力も不安定で、親会社が傾けば、ともに沈むしかない。古い機械で安く作らされ、利益もコントロールされる。徳明氏の見てきた限り、こうした会社は長続きしない。
■大手から学んだ「投資」の重要性
徳明氏が、現在150名を抱えるマレーシア工場と、6名のシンガポール営業所を任されたのは31歳のとき。若くして社長業に就けたことは大きかったと振り返る。
あるとき、大手企業のゴム製造現場を見学する機会を経験し、「ハンマーで頭を殴られたような衝撃」を受けたという徳明氏。
通常、ゴム製造の金型は素材によって汚れてしまい、3〜4日で洗浄しなければならない。大きな金型を外し洗浄する作業は時間も手間もかかる。そこで、大手では、金型を取り替えずに済むよう、金型を汚さない材料を開発していた。
また、キーワードを多用することも大手の特徴だ。「一発処理」「◯◯レス」といったキーワードを定めることで、作業に際して頭の中がクリアになり、ミスを減らすことはもちろん、工程の短縮などの工夫にもつながる。
大手が導入する設備や生産方法には、すべて理由がある。ひとつひとつの課題に対する「投資」の有無が、中小と大手のいちばんの差だ。資金力の問題はあっても、中小は中小なりに、毎月たった数万円でも投資に回せば、やがて大きく変わってくる。若くしてこうした考え方を学んだことで、同社もさまざまな改善を実現したという。
■職人に頼らないモノづくり
人口の少ないマレーシアでは積極的に外国人労働者を受け入れており、同社でも日本人、シンガポーリアン、マレー人、マレーチャイニーズのほか、ベトナム、ネパール、ミャンマー、カンボジアと多国籍から従業員が集まっている。ジャングルから出稼ぎに来ていたり、実家では農作業をしていたりと、初めて機械に触るような人たちだ。さらに、法律の関係もあって、労働者は長くても3年で辞めてしまう。そうした従業員たちを率いる徳明氏は、高度な教育を受けた優秀な社員を抱える日本の企業が、そうした海外に負けてしまっている状況に苦言を呈する。
「私はマレーシアで、いわば非常に不利な環境でモノを作っています。日本でも、何十年の職人に頼らずにモノを作れる方法を考えなくてはいけないのではないでしょうか。社長がいて、パートさんが何人かいれば回るようなシステムづくりに、少しずつでもいいから投資していくべきだと思います」
◇
両氏はともに、十代から海外で学び、若くして同社に入社、現場からスタートした。三男・勝臣氏(常務取締役)も加えた三兄弟がそれぞれの長所を生かして同社を支える様は、まさに毛利元就の「三本の矢」の逸話そのものだ。難しい時代にあっても、よく伸び切れにくいゴムのように、長く歴史を刻む同社。創意工夫こそ、資源に乏しい日本の製造業・中小企業の専売特許だ。

プロフィール
田口郁男(たぐち・いくお)氏
1976年生まれ。高校2年からアメリカに留学。南ミシシッピー州立大学卒業。日本帰国後、タグチゴム入社。その後、海外法人での勤務を10年ほど経験。常務取締役。
田口徳明(たぐち・とくあき)氏
1973年生まれ。高校卒業後、海外留学。日本帰国後、タグチゴム入社。2003年より海外勤務。2004年、シンガポール・マレーシア現地法人の代表取締役に就任。株式会社タグチゴムの専務取締役を兼任。
株式会社タグチゴム
〒124-0012 東京都葛飾区立石3-11-12
TEL 03-3694-6211
http://www.taguchi-rubber.com/
◆2016年2・3月号の記事より◆