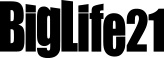株式会社カレン ‐ 情報を体験価値へと換えるプロ集団
株式会社カレン ‐ 情報を体験価値へと換えるプロ集団
◆取材:綿抜幹夫
年齢構成も前職も様々な同社の社員。藤﨑氏や同社の理念に共感して集まった『全員がプロをめざす』集団だ
IT業界の常識を覆す人材採用でオンリーワンをめざす
株式会社カレン/代表取締役社長 藤﨑健一氏
インターネットの登場以来、世界の情報量は増加の一途を辿り、情報検索や分析技術は日々進化し続けている。情報発信ツールがいくら増えても、情報分析ツールがいくら進化しても、商品に興味がある人にベストなタイミングで行動につながる有益な情報をいかにして届け、販売機会を最大化するかは、企業にとって頭の痛い問題だろう。
「株式会社カレン」は「ベストメッセージングカンパニー」を掲げ、デジタルCRM技術で、そんな企業の悩みを解決するマーケティングのプロフェッショナル集団だ。同社の理念に込められた藤﨑健一社長の思いを聞いた。
流通への興味からマーケティングの世界へ
藤﨑氏がマーケティングの世界に入ったきっかけは、就職の時までさかのぼる。1965年生まれの同氏が大学を卒業したのはまさにバブルの絶頂期。ほとんどの学生が金融系を志望する中、流通に目を向けたのが始まりだ。
「当時の流通は多くがメーカーと末端ユーザーの間に卸業者や小売業者が介在する屋上屋を重ねる仕組みでした。量販店は、価格統制に反する値引き販売をしたことで、メーカーからの商品供給を止められる。量販店が独占禁止法で訴訟するなどの問題が起きている状態でした。けれど消費者からすれば当然、安く買いたいし、いろいろ提案もしてほしい。
今後は、消費者が望んでいるものを直接届けるダイレクトマーケティングの時代が必ず来る、と確信しました」と、当時はまだ産業としては小さかった通信販売会社に入社。社会人としての一歩を踏み出した。
訪問販売部で学んだ情報分析の大切さ
しかし通販会社でダイレクトマーケティングを学ぼうという藤﨑氏の当ては、大きく外れることになる。というのも、最初の配属先は宝飾品と呉服を扱う訪問販売。商材についての知識はまったくなく、毎日個人の家を営業して回るも、最初の1年間は1つも売れない日々だったからだ。
あまりの売れなさに「これはもう続かないか……」とも思ったそうだが、小さい頃から野球で鍛えられていたせいか辛抱強さはあったという藤﨑氏は、辞める代わりに1つの決断をする。「3年は続けて、そのうちに事業所の営業500人の中で何とか1番になってやろう」と決めたのだ。
目標が決まれば次に必要なのは戦略だ。「売れるためにはまず家に上げてもらうこと、そのためには相手に合わせた情報を届けることが必要」と考えた藤﨑氏がまず取り組んだのが、住所・氏名・電話番号・職業はもとより、趣味・持ち物から友人に至るまで顧客1人ひとりの情報をできうる限り集めた「顧客台帳」作りだった。
そうして集めた情報を元に顧客にとって有益な情報を届けることだけに集中して活動を続けた結果、ある日努力がついに実を結ぶ。
「その方は幼稚園の園長先生で書道がお好きな方でした。僕はまったく書道には興味はありませんでしたが話を揃えようと勉強しました。にわか仕込みなので、知識の浅さは見抜かれていたと思いますが、私のためによく勉強して来たねということで家に上げていただいて。その先生が今度個展を開かれること、その時に着物を着て行かれることを聞くことができたんです。
ならば着物に合わせた宝飾品をご提案したらどうだろうと思い、真っ赤な珊瑚の指輪をお持ちしました。そうしたら個展の時に丁度いいかもしれないと言ってくださって。初めてお買い上げいただいたのがその真っ赤な珊瑚の指輪でした」
その1件がきっかけとなり、個展に集まっていた友人たちのデータもしっかり顧客台帳に記入。2年後に友人やその友人たちの趣味や家族構成、持っている置物や宝飾品などの情報で台帳がいっぱいになる頃には、紹介が紹介を呼び宣言どおり1番になっていた。
インターネットと出合い道を決める
ここでの「お客様情報の収集・分析が良い提案につながり、すばらしい提案をすれば喜んで受けてもらえる」という経験が、藤﨑氏のその後の人生の半分を決定付けたといっても過言ではないだろう。
「すばらしい提案をする仕組み、提案が喜ばれる仕組みをもっと広めたい」と考えた藤﨑氏は、見聞を広めようと自力でアメリカのダイレクトマーケティング会社の視察を手配し会社巡りを敢行した。
そこで1996年当時まだ普及し始めたばかりのインターネットとの出合いを果たし、今後情報の流れを変えるものだと確信。ぜひ日本で広めたいとの思いから帰国後退社して、高校時代の友人がコンサルティング会社として立ち上げていた「株式会社カレン」を基に、1997年、27歳の時にWebサイトやEメールを中心とするWebマーケティングサービスをスタート。まだ黎明期にあったこの分野のリーディングカンパニー的存在となっていく。
株式公開に失敗、株主からの株式買取請求、そしてグループ傘下へ
インターネット利用者に自社の存在を知ってもらうためのホームページ立ち上げビジネスが活況を極める中、その一歩先を行く顧客データに基づくWebマーケティングは、大手メーカーのマーケターの心を掴み、アップルコンピューターやAIGなど外資系に次々と導入された。
独自に、「Eメールマーケティング」とマーケティング手法を命名すると、システム企業やデジタル・マーケティング企業も市場参入し、会社も市場も成長することになる。
2004年には、株式公開を目指し、事業会社やベンチャーファンドから資金を調達し、システム投資、株式公開準備のための人材採用も進める。しかし、新興市場の規制強化により、株式公開は果たせなかった。
「デジタルCRMという事業を多くの人に知ってもらうには、株式公開は有効な手段と考えて取り組みました。株式公開できなかったことの無念さはありましたが、それよりもベンチャーファンドからの株式買取請求には心底困り果てました。身銭で買うことができる額を遥かに上回っていたからです。それまでが順調すぎたのかも知れませんが、この時に初めてお金に困りました」
ここで藤﨑氏は苦渋の決断を下す。大阪に本社を構えるサービス総合コンサルティング企業グループの傘下に入り、同社の子会社となったのだ。
再び独立を決意。モノづくりからアウトソーシングとインソーシング受託へ
社員とのミーティング風景
グループの傘下に入ったものの、価値観も違えば、事業の組み立て方も風土も全く異なっていた。藤﨑氏は自らが大阪へ転居する決断をし、カレンをグループの一員の会社とすべく、飲食チェーン店を顧客基盤に持つ同社との協業をめざして奔走した。が、結局、同社とのシナジーは出ないばかりか、手塩にかけてきたデジタルCRM事業自体の勢いが徐々に無くなっていった。
「そもそもなぜ、デジタルCRM事業をやりたかったのか? 大阪で悪戦苦闘する中、よく自問自答しました。その答えを見つけた時、覚悟を決めました。私自身のお金はもとより、親類縁者や応援してくださる方々からのお金を基に、カレンを譲渡してもらい再挑戦することを決めたのです」
昨年から再挑戦を始めたカレンの「お客様情報の蓄積・分析を通して顧客に喜ばれるベストな提案を行う」という理念、藤﨑氏の言葉を借りれば「ベストなメッセージングを作るカンパニーである」という核は、20年前と変わっていない。大きな転換は、マーケティングツールを開発・提供するというモノづくりスタイルから、既存のツールを使って企業のデジタルCRM業務をアウトソーシングとインソーシングで受けるスタイルへと舵を切ったこと。
「いくらいいツールでも使いこなせなければ宝の持ち腐れになってしまいます。いい物を提供してもお客さん側でうまく使いこなせないという悩みがあったので、私たち自身で運用・支援するアウトソーシング・インソーシングスタイルに切り替えました。それによりお客さんに喜ばれるのはもちろん、私が過去に体験してきたのと同じように、ベストな提案をし感謝される喜びをうちのメンバーも体験できるようになったのが大きなメリットです」と藤﨑氏は明かす。
メッセージングの要は個々の社員の力
現在、同社の顧客は自動車メーカーや家電メーカー、大手金融機関など購買の際に複数を見比べながらじっくり選ぶ商品を取り扱う企業が多いという。それらの顧客が想定する消費者に向けた最適なメッセージングとは一体どのようなものか。それは何も「直接モノを売る」ということだけに留まらないと藤﨑氏は話す。
「例えばカメラメーカーがめざすのは、ただ〝カメラを買っていただくこと〟だけでなく、気に入ってずっと使ってもらい、買い替えの時も同じメーカーで買ってもらうこと。そのためには購入者が喜ぶベストなタイミングで、体験したくなる情報を届けることが何より重要になるのです」
この場合まず同社が行ったのは、カメラを購入後、保証書の発行にはインターネットで自分の買ったカメラの番号と名前を入れてもらう仕組みを通して、いつ誰が何を買ったかという「顧客台帳」を作ることだった。
そしてその台帳をもとに、数日後にはカメラ初心者がまず困る写真データの保存先の案内を、そろそろもっときれいな写真が撮りたいなというタイミングで写真学校の紹介を、腕が上がり新しいレンズが欲しくなってきたところで広角レンズや望遠レンズの案内をという風に提案を進めることができれば、ちょうど欲しい物が手に入った購入者も、目的を達成できた企業も喜ぶ、ベストなメッセージングが達成された理想の状態ができあがる。
ただもちろん「ベストのタイミングで最適な情報を出す」ことは簡単ではない。時期が早ければ購入にはつながらず、遅ければ飽きて他社製品に流れてしまうデリケートなものだ。どのようにコミュニケーションを取れば最も喜んで買ってくれるのかを導き出すのは、購買者の行動パターンを分解して追及する人の力であり、それはマーケティングの肝でもある。
そしてだからこそ、それができる人材の育成に同社は今一番力を入れているところなのだという。
情熱を持ったプロ集団をめざして
より良いサービスを提供するため、全員一丸となり新たな挑戦を続けていく
約40人ほどいる同社の社員の顔ぶれは、下は20代の若者から上は50代の転職者、元主婦と年齢構成も前職もバラエティに富んでいる。そんな中、1つだけ共通するのは、同社の理念であり藤﨑氏の原点でもある「情報を分析しぴったりの提案をする喜びを世の中に広める」という夢に共感し、ぜひやってみたいと自ら手を挙げたこと。
新入社員として採用した中にはインターネットや広告業界の経験が乏しい人もいるが、人が成長するにはなによりその情熱が大切なのだと藤﨑氏は言う。
「その代わり、勉強しないともちろん付いて来られない世界です。社員に求めているのは、どんなにニッチな部分でもいいからプロになること。なので、全員に何のプロになるのかという〝プロ宣言〟をしてもらっています。
デジタル・マーケティングのシステム自体は世の中にたくさんありますが、〝それを使える人間〟というところにフォーカスして商売をしていこうというのが当社の特徴であり、ほかにはない強み。
だから当社の基盤は人であり、プロの育成、全員がプロをめざすというところにあるんです。今後はさらに、業界ごとのプロフェッショナルを事業家へ育てることをやります」
同社がこの採用方式を取り始めたのは今年の年初から。以前は自動車や家電メーカーなど同社顧客に関わる仕事がしたいIT経験者たちを採用・教育してきたが、「分析し提案することに喜びを感じることができる人を一人でも多く輩出する」という理念に共感する人の方が、成長速度も伸びしろも大きい傾向があり変更したのだという。
「今の一番の悩みも人。採用した人材が本当に成長できるのか、どんな体験機会を提供すればもっと成長するのか、いつも頭を悩ませている」と藤﨑氏。情報の氾濫で真に有益な情報の伝達が難しくなっている現在、マーケティング業界ではグローバルな規模で、オートメーション化が進んでいるようだ。
ただし、システムという道具が進歩しても、自分にピッタリのものをタイミングよく紹介してくれるサービスを設計できるプロ集団は少ないという。人材不足が叫ばれるIT業界の一般論にあえて背を向けた採用策の結果を含め、新しい挑戦を続ける同社の今後に注目したい。
藤﨑健一(ふじさき・けんいち)氏…1965年、静岡県生まれ。静岡県立浜松北高等学校、専修大学法学部卒業後、大手カタログ通信販売会社に入社。ユーザープロファイリング技術を学ぶ。アメリカ・シリコンバレー研修を経て、1996年に退社し、㈱カレンに参画。Eメール・マーケティングにはじまり、SNSツールやデジタル技術などを用いたデジタルマーケティングを多数の実績を残す。現在、株式会社カレン代表取締役。
株式会社カレン
〒105-0012 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル5F
TEL 03-6681-8480
http://www.current.co.jp