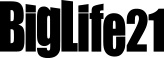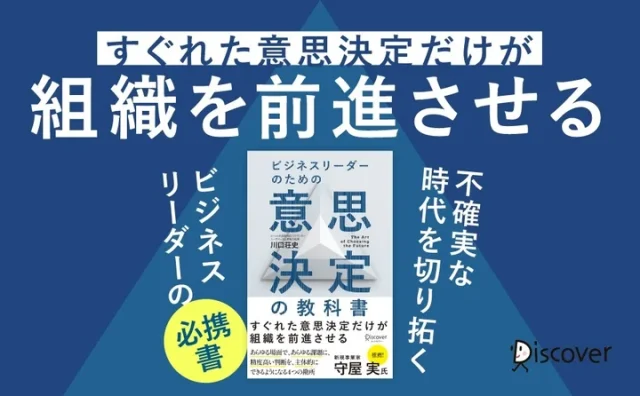コラム『日本人相手の誘拐は人質と遺骨で二度美味しい』
コラム『日本人相手の誘拐は人質と遺骨で二度美味しい』
◆文:加藤俊
小説『ブリキの太鼓』の主人公オスカルは、ブリキの太鼓を叩くことで、世界を風刺的に叙述した。その音色は、戦後ドイツが目を背けていた恥部、第二次世界大戦に向かう国内の狂騒、一般市民がナチスに加担したという事実を、冷徹に抉り出し断罪していった。市民はその罪悪感を、ナチスと時代のせいにしようとしていた。だが、太鼓の音が、目を覚まさせる。
「ドイツを見習え」とやたら煩い隣国の弁を真に受けるではないが、ドイツ人が過去に真摯に向き合う理由の一つとして、本書の影響は小さくない。
4月13日、独北部リューベックの病院で、著者ギュンター・グラスが死去した。87歳だった。今にして思うと、断罪されたがっていたのは、グラス自身だったと思えてくる。本書を通してナチス社会を容赦なく解剖し、「ドイツの良心の番人」とも言われたグラスだが、2006年に自伝『玉ねぎの皮をむきながら』で、実は、自身がナチスのS・S(ナチ武装親衛隊)に所属していた過去を告白している。
50年越しのこの告白は世界に衝撃を与え、ノーベル賞返上を要求する非難まで出た。しかし、グラスが20世紀の文学界を牽引してきたことは紛れも無い事実である。
そのドイツから南東に4,000キロ離れたシリアで、後藤健二、湯川遥菜両氏の遺骨奪還を求めた交渉が、ISILとの間で行われている。が、一向に纏まる気配がない。生きている間から安倍政権に見捨てられた両氏は、虐殺されて骨になっても家族の元に帰れないというのか。
想えば、後藤さん達もまた、事件を機に、過去をほじくり返されている。金の持ち逃げや風俗店の経営、色々な噂がネットを巡ったが、戦場の悲惨さを伝え、平和の尊さを訴える後年の姿勢は、グラス同様に瑕疵がつくものではないだろう。
むしろ、問題点が露わになったのは政府の方である。海外にいる邦人の保護が相手国の善意に頼るしかないことが露呈し、「テロ集団との交渉は行わない」との大義に逃げ込んだ先に、問題解決への気概は全く見えてこない。そこには、落ち度があったとしても、自国民を守るという姿勢が見当たらない。
自己責任の一言で切って捨てた世論といい、遺骨引き取り要求も行わない姿勢に苛立つ遺族は、新右翼団体「一水会」を通じて帰還交渉に乗り出した。ただ、ISILからの法外な資金要求は免れそうにない。
21世紀の世を諌める太鼓の音はいつ鳴るのか。聞こえてくるのは、「日本人相手の誘拐は人質と遺骨で二度美味しい」そんなテロリスト達の高笑いばかりである。