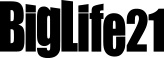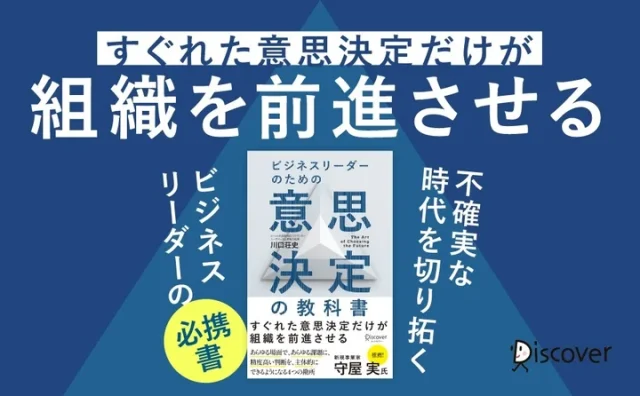M社のカサノバさんに教えたい─経営のことは近江商人に訊け
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ!12
M社のカサノバさんに教えたい─経営のことは近江商人に訊け
◆文:佐藤さとる (本誌 副編集長)

奴らの歩いた後には、ペンペン草も生えない─かつて遠方からやってきた彼らを江戸在来の商人たちは、こう妬んだ。
彼らとは、そう、「近江商人」である。
当時、江戸を目指したのは近江商人だけではない。東西南北の商売人たちが、当時世界最大級の都市となっていく江戸に向かった。そういった「メガコンペティション」状態のなかで勝ち抜けたのは、なぜか。それはいまで言うところの「現地化」に長けていたのである。
当時の文化的差異と移動手段とその距離を勘案すると江戸は全く異国である。
その異国で商売をするには、どうすればいいか─。
行商人集団だった近江商人は、その基本原則を早くから打ち立てていた。それが「他国者意識(たこくものいしき)」という考え方である。近江商人の憲法的な考えで「他国に出向いて店を構えるときは、常に他国者(よそ者)意識を忘れないようにする」というものだ。
その原点は、宝暦4(1754)年に70歳となった麻布商の中村治兵衛宗岸(そうがん)が、15歳の養嗣子に書いた書置きのなかの一節と言われる。この書置き条文は明治になって「他国へ行商するも、総て我事のみと思わず、その国一切の人を大切にして、私利を貪(むさぼ)ることなかれ、神仏のことは常に忘れざるよう致すべし」と翻訳されて、より分かりやすくなった。
分からない人のために、ワタシがヨミ下してみるとこうだ。
「儲かるからと言って、自分だけが利益をむさぼっていてはいけないよ。そこにいる人々の生活を忘れてはいけないよ、神様仏様が見てるんだから」
そんな戒めである。
耳が痛い言葉である。
とかく業績が伸びたり、地位が上がったりすると、人間という動物は図に乗るものである。ワタシなどはちょっと小銭が入っただけで、次こそは「世界を制覇だ」とか、「全てを覆い尽くしてやる! 俺様色で」とか言ってしまう。ああ、それではいかんのである。とかく商売をしたいなら、この「よそ者憲法」を心のなかに宿して拳拳服膺していなければならないのだ。
近江商人はこのよそ者憲法をベースとして商売基本法を組み立てている。よく知られる「三方よし」はその代表例だ。
三方とは「売り手」「買い手」「世間」の三つを指し、それぞれが良くないと商売はうまくいかないというもの。CSRや社会貢献などを先取りした示唆的な思想として知られるが、売り手と買い手のWIN-WINでなく「世間をよくしないと商売はうまくいかない」と言い切ったところに、近江商人の凄さがある。
「薄利多売」も近江商人の基本法である。いまでは大量生産、大量消費時代の代表的な販売戦略の一つだが、近江商人のそれはもっと哲学的で社会的だ。
「たとえ商品が品薄であっても余分な口銭を取らず、売り手が悔やむくらいの薄い口銭を基本とする考え方で世の中に害を与えないように商売を行うこと」が、薄利多売の本分なのである。うーむ。深い。
他にも「利真於勤(りはつとむるにおいてしんなり)」なる言葉がある。これは「商人が手にする利益は、権力と結託したり、買占めや売り惜しみをしないで、需給を調整して世に貢献する」という考え方だ。うーん、ぐさっ! である。
「天性成行(てんせいなりゆき)」という戒めもある。これは取引における基本を述べたもので、「自分の都合や勝手だけを優先させず、また思惑をせず、自他ともに成り立つことを考えること」を言う。だから損もあれば益することもあるのであり、損益は長期的平均にみることが大事という教えである。
「売って悔やむ」も良く使う。「先々の値上がりを期待して売り惜しみをしない」という商売理念である。
とにかく欲をかかず、目立たず、ひたむきに世間の役に立つことを念頭に商売に取り組む姿勢がそこにはある。
誰とは言わないが、進出した土地の文化やセンスを無視して、弁明を募る商売人たちにこそ、服膺してもらいたい言葉ばかりだ。
イマドキのビジネスは、だいたいそんな感じだ。