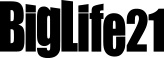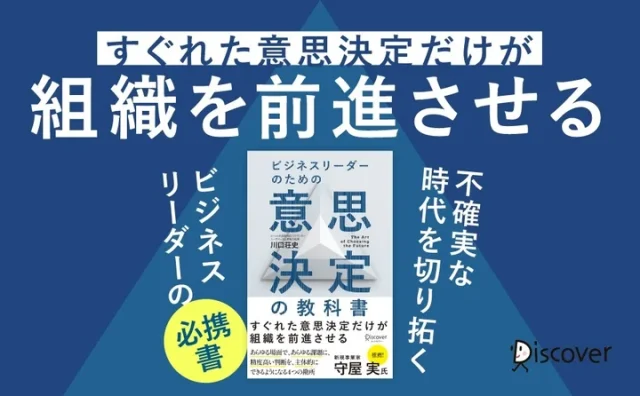株式会社土屋 代表取締役・高浜敏之が影響を受けた本
大学で哲学を専攻し、その後介護福祉の道へと進んだ(株)土屋 代表取締役・高浜敏之は、常に思考と実践の中を歩み、その過程でホームレス支援活動や難民支援活動、障害者運動等の社会活動家としての足跡も刻んできました。
一方で、アルコール依存症に陥り、生活保護を受給する時期もあるなど、人生のどん底も経験した高浜が自らを方向づけた本の数々、その一部をご紹介します。
高浜敏之が影響を受けた本 5選
①「聴く」ことの力: 臨床哲学試論 (鷲田清一)
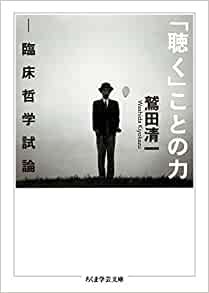
画像引用: Amazon
当時、私は大学で哲学・文学を学んでいて、その頃付き合っていた同窓の女性(現在の妻)に勧められて本書を手にしました。
「聴く」という受動的な行為による他者理解、哲学の可能性を示した本ですが、著者の哲学者・鷲田清一氏の切り口が面白いんですね。
哲学者は一般に哲学の素材を使って思考しますが、鷲田氏はファッションなど、日常に近い所を自分の思考する場所に選んでいて、本書ではまさにケアの現場が取り扱われていました。
その中で、とりわけ印象深かったのが、精神科医の中井久夫氏が不眠症の女性と向き合う場面です。
女性は通常ではありえないほど脈が速く、眠れない。中井氏は彼女と向き合っているうちに、自身もそこに同期して同じような脈を打っていたというんです。
通常、私たちの悩みや苦しみは、「私とあなたは別の存在である」という、場合によっては孤独にも帰結するところから生み出されるものです。
私自身、この自他の分離によるネガティブな有りようが哲学や文学を志す出発点となっていて、この自他の壁、自己と世界を遮る境界をどう突破していけるのかがテーマでもありました。
その営為の一つが私にとってはアートであり、アルコールであったわけですが、それが描かれたのがこの場面で、自己と他者が交流する機会の一つにケアがあったということです。
しかも、ここでは情動やパッションのレベルで人と人とがつながっている。自身と世界が切り離されているということ自体、人間の意識がもたらした産物であると捉える現象学的な視点からの交流の描き方で、すごく魅惑されましたね。
当時、私の研究対象であったジョルジュ・バタイユは、「すべて動物は、世界の内にちょうど水の中に水があるように存在している」という言葉を残しています。
人は動物と異なり、世界と自己の連続性が絶たれた状態にあり、そこから死の意識が生まれ、その予見から不安も生まれると解釈されますが、私自身、ずっとそのようなテーマ圏を巡り、自他を乗り越える方法を探していた中で本書と出会い、自分が考えてきたことの延長線上にケアを見出しました。
これは、哲学・文学の研究者を志していた私と、介護士という仕事を選んだ私にとっては非常に連続性があるもので、自分の思考と、その実践の場があるということを教えてくれ、その橋渡しをしてくれたテクストとして、非常に感銘を受けましたね。
②両利きの経営(増補改訂版)-「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く(チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン)

画像引用: Amazon
介護士として歩んだ後、介護会社の立ち上げに関わりましたが、企業戦略について書かれた本書は、「この先、ビジネスをやっていく」という決断が付いた中で読んだものです。
当時は、重度訪問介護など新規事業開発の最中でしたが、そこでよく目にしたのが、新しいことを始めようとすると、既存事業をしている人が必ず反対するということです。
不思議に思いましたね。というのも、既存事業も元々は新しいものとして生まれ、それを立ち上げていなかったなら雇用も生み出されず、彼らもそこで働いていない。
しかも、新規事業により支援を受けられる人がいて、ビジネスとして成功すればキャリアアップもできます。可能性の宝庫なのに、どうして反対できるんだろうと。
疑問に感じながら事業を広げてきた中で、本書はまさに、そういった自分の経験が言語化されていると感じました。
ビジネスというのは、既存事業の深化と新規事業の探索を同時に行わないと発展しないものです。そうでなければ企業は停滞し、事業そのものが厳しくなっていく。
ただし、両者は非常に相性が悪く、同じ場所で同じ人たちがこれを同時にやろうとすると必ず争いが起こります。
というのも、新規事業は人的リソースを奪うことで既存事業を危機にさらす可能性があり、新規事業がトップに躍り出ると、社内における優位性や格付けも変わっていきます。
「かつての成功体験が未来の失敗を準備する」ということですね。
クリステンセン博士の『イノベーションのジレンマ』でも取り上げられているように、成功体験に固着したソニーは、新興企業のアップルに敗退しました。
これは企業の宿命でもありますが、これを乗り越えるには「両利きの経営」、すなわち既存事業の深化と新規事業の探索を同時にできるような環境を会社の中で作ることです。
そして、それをトップのリーダーシップの下に、しっかりと社内に宣伝していく。これが、イノベーションのジレンマに陥らない道だと提唱されていますが、当社がこれに陥らなかったのは、ある意味で偶然です。
かつてデイサービスで成功したときに、それだけでやっていこうとはならずに、重度訪問介護分野に進出したから今があります。
現在推進している定期巡回やカレッジ事業がなかったら、当社が5年後に倒産していたという可能性もゼロではないはずです。
ビジネスは常に風化していくものですが、本書は、我々の成功体験をしっかりと言語化してくれただけでなく、今後も当社が「両利きの経営」に向かうための指針として、非常に大切だと考えています。
③貧困のない世界を創る(ムハマド・ユヌス)
画像引用: Amazon
貧困問題の解決には、以前より多くのNGOやNPOが取り組んできましたが、それらと比したときのムハマド・ユヌス氏の特異性は、彼がそれをビジネスで達成したという点にあります。
これまで非営利活動とビジネスは対立関係にあると捉えられてきましたが、彼は本書で両者を融合させ、社会問題を解決する新しい概念として「ソーシャルビジネス」を打ち出しました。
私は以前、社会活動家として障害者運動にも参画していましたが、この運動のバックグラウンドに、実は貧困問題が存在します。
発展途上国(第三世界)と先進国の貧富の格差は、先進国による貧困国の搾取が要因だとして、そのシステムに抗する思想的実践が1960年代に生まれました。
これは若者たちが資本主義と真っ向から対峙した60~70年代の学生運動に端的に見られますが、やがてそれは敗北します。
その結果、一部は過激化してテロを起こし、一部は国内の第三世界(釜ヶ崎や山谷など日雇い労働者の居住地等)における闘いに身を投じます。障害者運動も、その一つとして70年代に生まれました。
闘いに敗れた若者が、新たな抗争の場として選んだのが障害者施設であり、障害者運動の先駆けである府中療育センターや「青い芝の会」の闘争は、実は彼ら若者と障害者の協働によって戦われていたんです。
こうした中で、障害者運動をしていた私自身も、ビジネスは敵だという思いがありましたが、紆余曲折を経て、自分自身が、こともあろうに株式会社の担ぎ手の一人になりました。
けれど経営をする中で、ビジネスとして社会課題の解決を行うことのポジティブな面も見えてきたんですね。
企業が成長するにつれスケールメリットが働き、キャリアアップや高収入も得られることで、以前は介護業界に参加しなかった人たちが参入し、すそ野が広がることで問題解決も近くなる。これは悪いことばかりではないと。
一方で、かつて私が経営者を敵がい視し、攻撃したように、今度は私が現場から攻撃されるようになり、なんともいえないジレンマを抱える中で、自分たちの営みをしっかりと言語化し、説明するための理論的な装置が必要だと考えるに至りました。
この時に出会ったのが本書の「ソーシャルビジネス」という言葉です。
これはビジネスとNGOという敵対関係にあった両者を和解させた概念であり、私自身、ビジネスとして社会課題の解決に向かうことに、それまではなんとなく後ろめたさを感じていたり、価値観のブレがありましたが、この言葉で迷いがなくなりましたね。
右でも左でもない、真ん中をやっていくんだと、決断がもたらされたという感覚がありますし、他者に対しても我々の思想を明白に語れるようになったんです。
④対立の炎にとどまる――自他のあらゆる側面と向き合い、未来を共に変えるエルダーシップ(アーノルド・ミンデル)

画像引用:Amazon
著者のアーノルド・ミンデルは、プロセス指向心理学を開発した人で、本書ではそれを実践的に応用した「ワールドワーク」について語られています。
ワールドワークにおける彼のセッションの舞台は、パレスチナ人とイスラエル人の対話、南アフリカにおける黒色人種と白色人種の対話など、常に対立のある場所です。
そして彼は、その対立を乗り越える方法として、感情を否定せず、むしろそれを表現することを選びました。
被害者が加害者と向き合う中で湧きあがる怒りや恨みの感情を、否定することなく表現する。ないしは表現することが許される場を作ることで、真の平和がもたらされるとする立場から、彼は対立の場を意図的に作り出します。
本書を読んだのは、私がアルコール依存症になり、生活保護を受けていた30代の頃ですが、障害者運動に従事していた自身の経験からも非常に腑に落ちるものでした。
というのも、私が健常者として障害を持つ人の中に入っていくと、彼らは私に、自分を虐げ、子宮を奪い、施設に放り込んだ健常者を投影し、支援する私が障害者差別の当事者だと認定され、事あるごとに糾弾・攻撃されるわけです。
障害者運動の中にいる健常者は、自らに対する当事者の怒りと向き合い続けながら、当事者とともに社会に対して怒りを表現するという二つの闘いを生きなければならず、とはいえ傷ついた人たちの情動を否定することはできない中で、ジレンマを抱えざるを得ないんです。
そうした中で、この本の思想である、「対立を乗り越えるために、まずは自分の内側にある怒りの炎を表現するところから出発する」というスタンスは説得力がありました。
社会活動家を生きるということは、常に対立がある場に身を置き、弱者とされる人の権利を闘いを通じて取り戻すというものです。
けれど、そこには攻撃する側と受け止める側の平行線も感じられ、かつ加害者であることが被害者であり、被害者であることが加害者であるという面もあり、真の解決や和解が見えなくなっていく不毛な過程でもあります。
本書の手法は、それでも対立がある場に身を置くことの意味を再発見できるものであり、自身の権利を傷つけられた当事者に寄り添うという選択を正当化できる理論だと感じましたね。
⑤深い河 (遠藤周作)
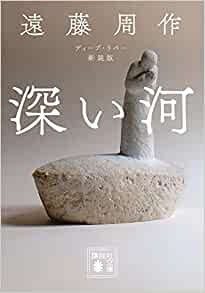
画像引用: Amazon
大学生の時に読んだ本ですが、遠藤周作は高校時代から愛読していました。
中上健司と三島由紀夫が一番好きでしたが、遠藤周作は彼らほど難解でもないし、テーマも分かりやすいけれど深みがあって、息抜きのように読んでいた覚えがあります。
当時働いていた飲食店の上司(元暴走族)に貸したら、すごく感動して、一緒に飲みながら語り合った記憶がありますね。
本書を流れるのは、聖地ガンジス川です。様々な歩みや記憶、バックグラウンドをもった人々が、旅の最中に出会う場所の象徴としてガンジスは描かれ、すべての多様なものを呑み込んでいく。
そこでは、正しいものと間違っているものを切り分け、一方を称賛し、他方に制裁を与えるという道徳律と一体化した宗教観ではなく、清濁併せ呑むような、ありとあらゆるものを、良いも悪いもなく、母なる大地のように受容していくような、包容的なイメージがあります。
私はその頃、ポストモダニズムを学んでいましたが、それは言うなれば父的な権力に対する闘いであり、フェミニズムに見られる、女性的なるものをどのようにして再評価し、社会の中に浸透させていくかという、社会の解体にも似た学問で、私自身、存在を否定するのではなく肯定するということを、どのように社会の中で形成していくかをずっと考えてきました。
それはもしかしたら、本書で描かれたガンジス川のような場所を、現代社会の中にどう作っていくかということだったのかもしれません。
土屋は、元をたどるとデイサービスから出発し、できるだけ広く深く他者を受け入れるような場を作っていきたいという思いで歩んできました。
どこのデイサービスでも断られるような方々を受け入れて、「困った時は土屋さん」だと言ってもらえていたんです。
その延長に今の株式会社土屋がありますが、新しく作った当社もその記憶をしっかり踏襲していこうという思いの下、「土屋」という名前を付けました。
難病・重度障害をお持ちの方は、現代社会の中で生きていくことが難しい面もあります。
けれど施設や病院という場所に排除されるのではなく、社会の中に参画できるような、そのためのツールとしても、当社は重度訪問介護を広げていきたいと考えています。
これは、現代社会に「深い河」を再現させることなのかもしれないと、改めて今、感じています。
◎プロフィール

高浜 敏之
1972年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学文学部哲学科卒。大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。2020年8月に㈱会社土屋を起業。代表取締役兼CEOに就任。2023年1月には、重度障害者を24時間在宅で支援する重度訪問介護事業所「ホームケア土屋」を全国47都道府県に広げる。ALSなどの難病や重度の障害があっても、望む地域で望む人と安心して暮らせる社会の実現を目指し、日々奔走している。
◎企業概要
会社名 :株式会社土屋
URL :https://tcy.co.jp/
所在地 :岡山県井原市井原町192-2 久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜 敏之
設立 :2020年8月
事業内容 :障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業、介護保険法に基づく居宅サービス事業、講演会及び講習会等の企画・開催及び運営事業、研修事業、訪問看護事業